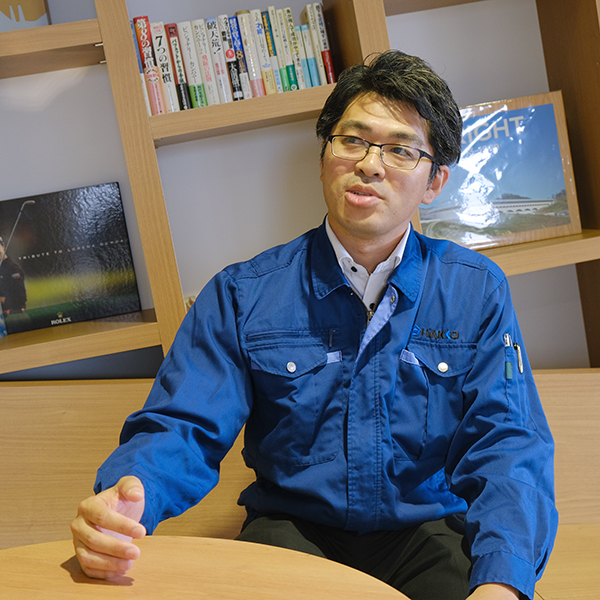電子製品の生産を支える“ステーション型はんだこて”に衝撃を受けて入社
私は種子島出身で、鹿児島高専の制御工学科でロボットの技術を学びました。自ずと将来は工業系の仕事に就くものだと漠然と考えていたぐらいで、はんだこてを作りたいという強い気持ちで就職活動をしていたわけではありません。
そもそも私にとって“はんだごて”は、普段、あまり意識することのない対象でした。白光に関心を持ったのは、“私が知らないはんだこての世界”に衝撃を受けたからです。意識していなかった道具を実際に作っている会社があり、しかも一般生活者ではない、工場に販売している。また、主力製品は、こて部とは別に本体があるステーション型はんだこてと言われるものです。もちろんはんだこては、中学の技術・家庭の授業で使用した他、高専時代も使っていました。
しかし、いずれも使用していたのは、棒こてと呼ばれる道具です。コンセントにつなぐと、電気がヒーターにつながり、5分ぐらい待たないと使えるようになりません。それに対してステーション型は、電源を入れて20秒か30秒で使えるようになります。また現在の温度が確認できる表示部も備えています。様々な電子製品が生産される背景に、このようなはんだこての存在があることを知ったことが衝撃的でした。
白光が本社を構える大阪と種子島は昔から縁があります。種子島に伝来した鉄砲を、日本で最初に製造したのが大阪府の堺でした。また私の親の世代は、学校を卒業して大阪で就職することが珍しくありませんでした。私の両親も大阪で働いていたこともあり、個人的にも大阪は馴染みのある土地でした。就職活動では将来、種子島に戻ることも想定し、東京にあるロケット関係の会社も受けましたが、結果的に白光に入社しました。
入社後は研修期間を経て、商品開発課に配属され、以来、製品内部の基板や電子部品の配線などの電気設計を担当し、2年ほど前からは、マネージャーとして電気設計領域のマネジメント業務を担っています。
大切なのはユーザーにとっての使いやすさ。海外市場も意識した商品開発
入社してすぐに悟ったことは、学生時代に勉強したことは、実務では全く通用しないということです。学生時代の勉強は、テストのための勉強です。先生がテストに出す範囲を勉強して、結果が良ければそれで終わりです。
しかし仕事ではそういうわけにはいきません。「イチから商品を作りましょう」と言われても、どうして良いのかわかりません。学校で学んだ知識を仕事に活かすにしても、改めて勉強し直さなければなりませんでした。技術者としてのターニングポイントがあったとすれば、入社1年目にそう思い知った瞬間です。
それから22年が過ぎた現在も確固とした自信はありませんが、開発の仕事にはやりがいを持っています。自分が電気設計を担当した商品が発売に至って、お客様のところに届いてご好評をいただければ、それが次の商品のモチベーションにつながります。ユーザー評価のためにお客様を訪問した際に、自身が設計した製品が何台も並んでいれば嬉しいですし、インターネットのレビューで高評価をいただいているのを見つれば自信にもなります。
商品開発で大切なことは、ユーザーが求める使いやすいものをいかに作るかという視点を持つことです。当社の製品は世界60カ国の方にご利用いただいていますが、地域によって好まれる操作感は異なります。私が入社した頃はプロダクトアウトで開発することが多かったのですが、最近はユーザーに実際の仕様を確認していただくフェーズが組み込まれています。
また、海外の人が違和感を持つカラーリングを採用しないなど、グローバルな視点を取り入れるよう変化してきています。日本だけではなく、海外にもお客様がいて、そのお客様が求める使いやすさを追求する。私自身もそういう視点が持てるようになりました。
棒こての時代は、つまみを回したら使えるような単純な仕組みのはんだこて以外に選択肢がありませんでしたが、それでもお客様のニーズも満たされていました。デジタル化して選択肢が広がったものの、はんだこてとしての基本性能が大きく向上したわけではなく、管理のしやすさや操作感などの付加価値がついただけです。いくら高付加価値でも、お客様にとって使いづらい機能であれば意味がありません。
若い頃はとにかくがむしゃらに働いて、今となっては当たり前になってしまったことも沢山あります。自分の中で知り得なかったことが当たり前になっていくプロセスは、振り返ってみると、すごいことだなと思います。
自分のカラーを出した設計ができる魅力。時代の変化に順応できる組織へ
これまで特に印象に残っているのは、アメリカのソフトウェア設計者と共同開発をした経験です。メカ設計の先輩と2人、毎月、アメリカに渡航し、1週間滞在して設計し、帰国して試作品を作って、翌月アメリカに持っていくということを繰り返しました。
スキル不足を痛感する場面が多く、苦労しましたが、約1年半、文化が全く異なる国を頻繁に訪れて仕事をするという経験からは、得るものも沢山ありました。その後も設計で海外に行くことや、量産地の東南アジアを訪れることがありますが、海外での仕事は、日本にはない新鮮な経験が得られて面白いです。
白光の魅力は、良い意味でルールが決まっていないことです。ものづくりの方法に正解はなく、1つの結果を得るために様々な方法を採ることができます。その意味でも白光には決められたルールは設けておらず、設計者の発想次第で自由な方法を提案できます。その枠がないことを難しいと感じる人もいますが、あらかじめ設けられた枠の中で設計をすると“作業感” が出てしまい、その瞬間に設計という仕事は面白みが失われます。適度な自由さがある中で自分の色を出した設計ができるところが、白光の商品開発の面白さです。
また、福利厚生も充実しています。社員食堂があり、昼食代を補助してくれる制度もあります。さらに、一緒に働く人たちに、気さくな方が多いことも魅力です。
一方で、時代はどんどん変わっていきますので、その変化に順応できる組織を作らなければならないという危機感もあります。自分の中の成功体験や失敗経験に拘泥せずに、時代に合わせた働き方、考え方ができるチームを作っていきたいです。
商品開発課では、1製品に対して、電気、ソフト、メカの技術者が3人でチームを組み設計業務を行っています。社内のグループウェアで全プロジェクトの進捗状況を共有し、全員、同じフロアで仕事をしていますので、行き詰まっている人がいればすぐに分かります。お互いに助け合いながら仕事をしています。
自分の仕事の範囲を限定してしまうような働き方は寂しいと思います。担当に関係なく、いろいろなことに積極的に関わっていただける方、どんなことでもみんなと一緒に親身になって仕事ができる方にご入社いただければ嬉しいです。